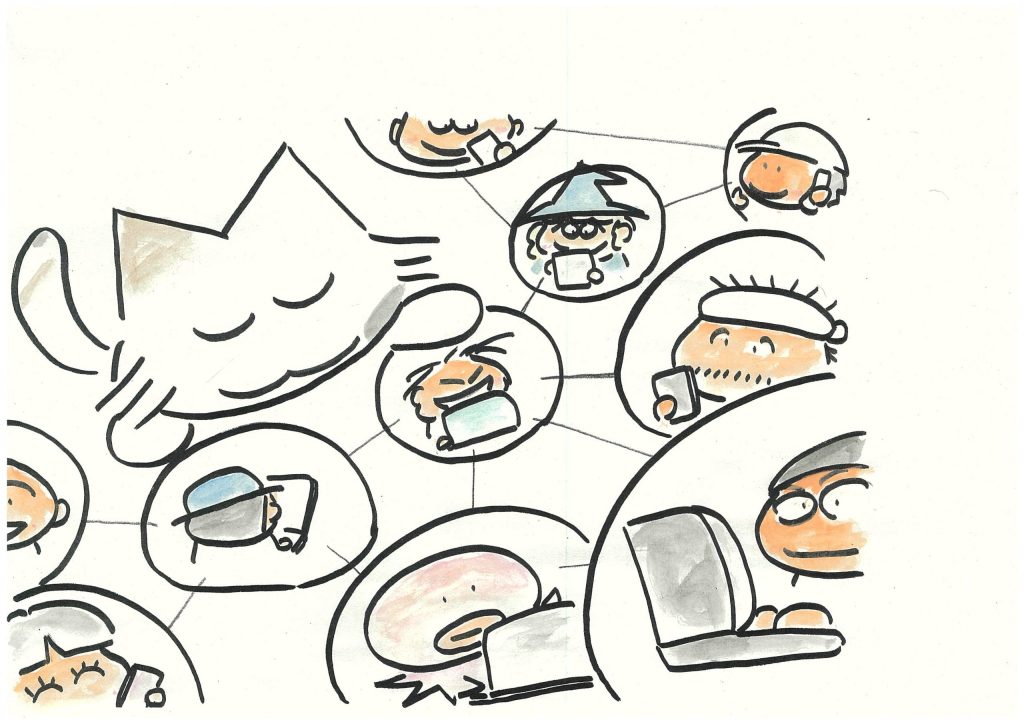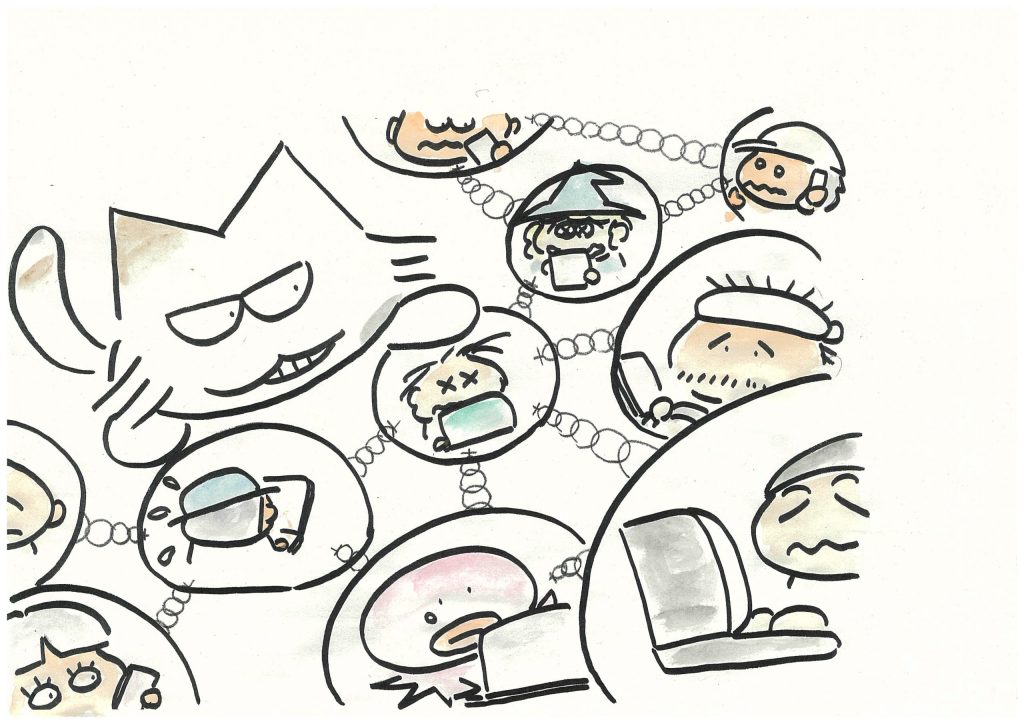2月23日の日経新聞経済教室、齋藤卓爾・慶応義塾大学准教授の「経営人材育成、早期・計画的に」から。
・・・つまり日本での企業統治に関する議論はバブル崩壊後の不祥事、業績低迷の原因追及として始まったのである。そして統治構造は、取締役会規模の縮小、海外機関投資家の持ち株比率の上昇などにより徐々に変化し、2012年発足の第2次安倍政権の一連の企業統治改革により大きく変化した・・・
では企業統治改革により日本企業の低業績は改善されたのか。各国の改革効果を検証した研究は、最低限必要な社外取締役の人数や比率の設定が業績を向上させたことを報告している。だが日本の改革が業績を明確に改善したという結果はこれまで得られていない。
売上高30億ドル以上の日本企業360社を含む30カ国約2千社の国際比較によると、日本企業の業績は14年から16年にかけて改善したが、その傾向は続かず、国際的にみて依然低水準のままだ。またよりリスクをとると大きくなると考えられる利益率のばらつきも、12年以前と同様に国際的にみて最低水準にある。社外取締役を選任した企業群の業績が改善したという傾向もみられない。企業行動でみても配当や自社株買いなど株主還元は増えたが、改革が目指したリスクテイクに関しては、設備投資や研究開発投資が促進されたという傾向はみられない。
長年日本企業の行動そして業績が大きく変わらなかった理由の一つとして、経営者の育成・選任が挙げられるのではないだろうか。適切な経営者の選任は企業統治、特に取締役会の最も重要な役割とされている。
米国では経営者の姿が時代とともに変化している。ピーター・カペリ米ペンシルベニア大教授らは1980年と2001年の米誌フォーチュンが選ぶ大企業100社「フォーチュン100」の経営者を比較し、若年化や最初の就職から経営職に就くまでの期間の短期化を報告している。カロラ・フリードマン米ノースウエスタン大教授は1935年から2003年までの経営者の変化を検証し、1970年代中ごろから生え抜きの経営者が減り、経営人材の会社間移動が増えたこと、経営学修士号(MBA)の学位を取得した経営者が増え始めたことを示した。
経営者属性の変化の理由として情報技術や経営管理手法の進歩、企業の巨大化、事業のグローバル化、多角化に伴い、経営者に求められる経営能力が特定の企業だけで通用する企業特殊的なものから、どの企業でも通用する一般的なものに移ったことを指摘している・・・
しかし日本企業の社長のキャリアパスはこの30年間大きくは変化していなかった。
近年、女性役員の登用が進むが、調査対象の社長で創業家以外の女性は1人もいない。外国出身の社長も極めてまれだ。社長に就任した年齢は90年以降一貫して60歳で、平均的には社長は若返っていない。入社年齢をみると、91%の社長が30歳までに入社しており、この比率は90年の81%から上昇している。
経営能力を見込まれたと考えられる41歳以降に入社した社長の比率は、90年の13%から7%に低下している。銀行の役員や官公庁の幹部などが、事業会社に経営者として移るケースが以前より減っているためだ。変化の象徴として注目されるいわゆるプロ経営者は、それを補うほどには増えておらず、近年むしろ内部昇進の社長が増えている。
かねて日本企業特有の遅い昇進は、リーダーの形成に不利であることが指摘されていた。社長就任者の昇進は他の社員と比べて特段早くなく、またこの30年間に早まってもいない。平均的に内部昇進の社長は入社から部長昇進までに約22年を要し、46歳ごろに部長職に就いている。これは一般的な部長昇進年齢とほぼ同じだ。そして入社から部長昇進、部長から役員昇進までの期間はむしろ長期化の傾向がみられる。
一方で社長就任年齢は変わらず、役員から社長就任までの期間は顕著に短くなっている。つまり内部昇進の社長のプレーヤー、中間管理職としての期間が長くなる一方で、役員としてトップマネジメントを経験する期間は短くなっている・・・