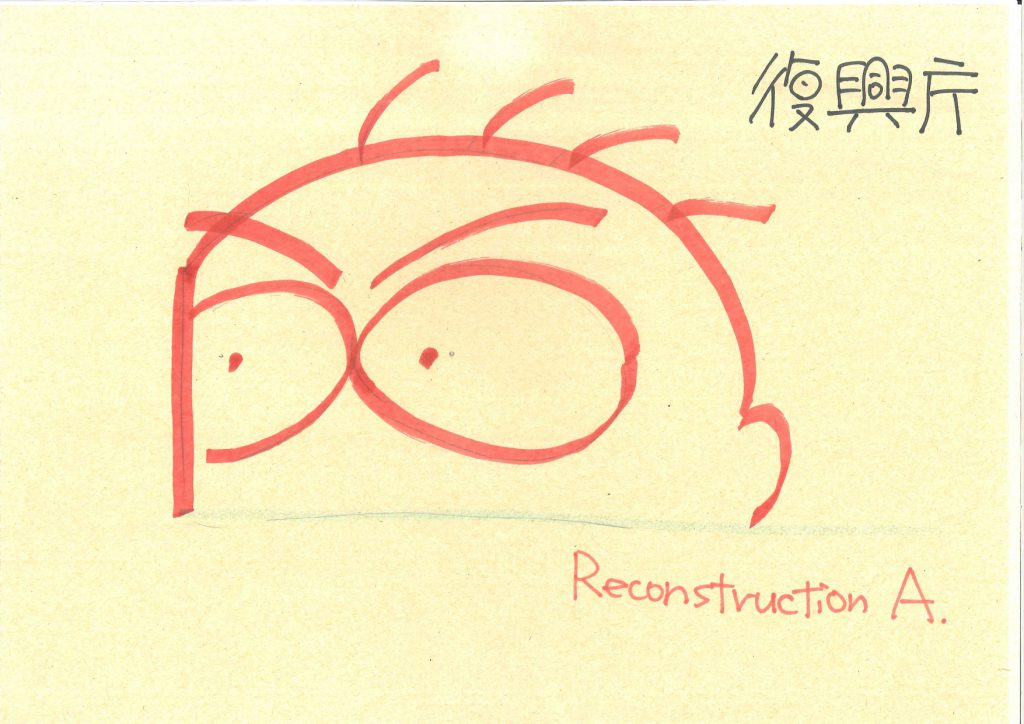日経新聞夕刊「人間発見」、3月10日の週は、中島茂・弁護士の「人を大切にする「司法社会」へ」でした。3月12日の「企業行動憲章で反社絶縁宣言」から。
・・・当時は地上げや債権回収、スキャンダルのもみ消しといった場面で、企業が総会屋や暴力団を頼っていました。一度不法勢力を利用すれば、金品の供与にとどまらず融資や取引の無理強いなどへと拡大し、とことん食い尽くされます。顧問企業や「中島塾」でそう訴え続けました。
私は「名もなく美しく」でいいと思っていたのですが、反社会的勢力と対峙する姿勢は徐々に知られるようになりました。
94年に役員が事件に巻き込まれた写真フィルムメーカーから、リスク管理担当弁護士として招かれました。私にとっても「言行一致」が問われる局面です。役員の警備体制を見直し、警察との連絡を密にして……。事案の性格上詳しくは語れませんが、2年間、大変な日々を送りました。
株主総会が無事終わった後、会社の幹部が「よく引き受けてくださいました。ありがとうございます」としみじみ言ってくれました。うれしかったですね。弁護士にとって最高の報酬は、やはりクライアントからの感謝の言葉です。
96年には大手百貨店の利益供与事件が起き、大手証券会社による総会屋への巨額の資金提供も発覚。中島さんが「発見」される。
突然、経済団体連合会(経団連、当時)から連絡があり、「信頼回復に向けて、企業行動憲章を書き直したい」との依頼を受けました。初めてオフィシャルというか、少し「広いところ」に出ることになったのです。企業の法務担当者と議論して「反社会的勢力とは断固として対決する」という一文を書き入れ、総会屋などとの絶縁を改めて宣言しました。
97年には、当時の都市銀行と4大証券会社が総会屋への利益供与事件で摘発されます。日本の企業社会が大きく変わった最大のきっかけとなった事件です。経営者ら36人が逮捕され、69人の役員が辞任に追い込まれ、1人の経営トップが自ら命を絶ったのですから。あの時に金融界は初めて、本気でコンプライアンスに取り組まなければ、と思ったのです・・・