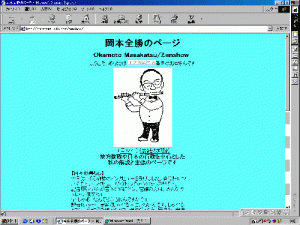【異質なものとの共存】
もう一つ、ヨーロッパで考えたのは、異質なものとの共存です。それは、次のようなことです。
ドイツでもパリでも、街でイスラーム系と思われる人をたくさん見かけました。もちろん黒人を始め非ヨーロッパ系の人もです。特にパリでは、バスがそのような人たちが集住している地区を通ってくれました。
白人であっても、東欧・南欧と思われる人、すなわち典型的ドイツ人やフランス人でない人も多そうです。私には、明確には区別はつきませんが。
ホテルで洗濯物を取りに来てもらったら、スカーフをかぶった中東系の若い女性でした(私と彼女で、英語でやりとりするのです。もっとも、アメリカ人としゃべるよりは通じたかも)。
フランスは総人口が6、000万人、うちモスリムが500万人、1割近くと推定されています。パリでの密度はもっと大きいでしょう。
パリには昔から、いろんな国の人がいます。ヨーロッパだけでなく、かつて植民地であったアフリカや東南アジアからの人たちもです。数多くの外国人を受け入れてきました。もちろん日本人の画家も。しかし、なぜモスリム(イスラム教徒)だけが「問題視」されるのでしょうか。そして、なぜ近年問題になったのでしょうか。
帰国して本屋で、内藤正典著「ヨーロッパとイスラム-共生は可能か」(岩波新書、2004年)を見つけました。そこに、切れ味よく経緯と分析が書かれています。
私の理解では、次のようになります。
ヨーロッパは、ヨーロッパ『文明』を受け入れるという条件の下で、外国人を受け入れてきました。その文明とは、基本的人権の尊重であり、政教分離です。それを受け入れれば、たとえ『文化』が違っても、受け入れてきたのです。
中華街ができても、日本のラーメン屋ができても。その点、フランスに移住した外国人は、東欧系であれ、アフリカ系であれ、アジア系であれ、ヨーロッパ『文明』に帰依したのです。
しかし、イスラームは政教分離ではなく、近代ヨーロッパ『文明』の「啓蒙主義」と相容れないものがあるのです。
さてこの点、日本はどうでしょうか。日本は、ヨーロッパ文明圏に入りましたが、日本文化と異なる文化を持った人たちが入ってくることに、まだ抵抗が強いようです。文明の違いの前に、異文化の人たちを受け入れる努力は少ないようです。そして、彼の地のような議論は、あまりなされていません。
もちろん、ヨーロッパ諸国は、地続きであることと、植民地支配の「負の遺産」を抱えているという背景もあります。でも、それを言うなら、日本も植民地支配の過去があります。また、ボートピープルという難民が来たこともありますし、北朝鮮からの「脱北者」受け入れもあります。
「花の都パリ」「国際都市ロンドン」にあこがれて、日本からも多くの人が渡りました。それを、彼の地・彼の人たちは受け入れてくれたのです。東京が「国際都市」を標榜するのなら、あるいは諸外国の人から「あこがれの地」となるためには、異文化の人を受け入れる雰囲気が必要でしょう。
「パリやロンドン、ニューヨークには行くが、外国人は受け入れない」では、尊敬されませんよね。
さて、もう一つ、ヨーロッパでの異質な文化受け入れの努力についても、述べておきましょう。先に紹介した、羽場久み子著「拡大ヨーロッパの挑戦」には、25もの国が統合される際の「苦しみ」も書かれています。
私たちから見ると、ヨーロッパはキリスト教という共通の歴史を持った「一体感あるまとまり」と思えますが、内実はそうではありません。キリスト教だって、カトリック、プロテスタント、ギリシャ正教と異なります。民族も言葉も、そして文化もかなり違います。
そして、この半世紀、西側資本主義国と東側共産主義国とに別れ、対立してきたのです。それは、自由主義経済の定着発展度合いの違いから、民主主義や自由主義といった政治の仕組みと運営の違いなども違います(新しい国をつくる努力については、別に書く予定です)。
さらに、経済力が違います。1人あたりGDPでは、EU平均の半分程度でしかない国もあるのです。
これらの違いを前提として統合するには、かなりの努力が必要です。均質化するのでなく、「多様性を持ったままの統合」です。